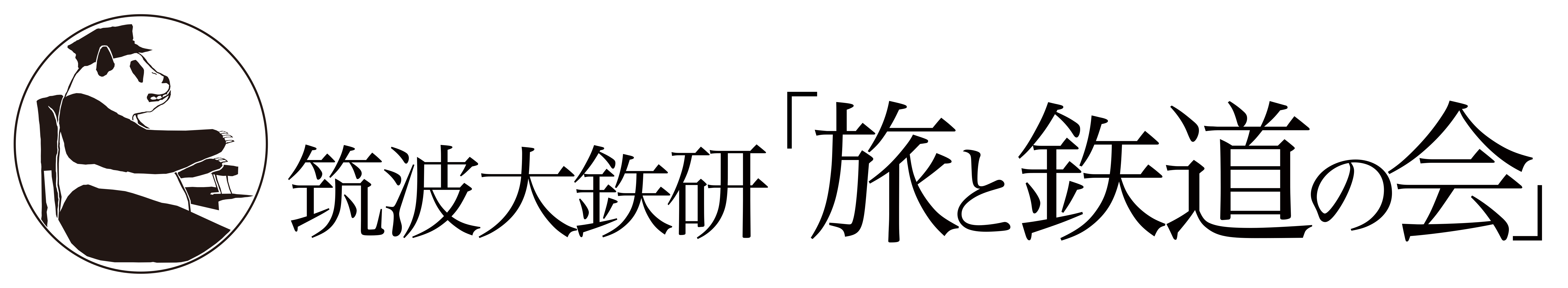2024年新春旅行記(東京・伊豆大島)
旅人 白鶺鴒
1.はじめに
旅と鉄道の会では,新春旅行はその年に卒業・修了する学生が記念として行き先を決めるのが恒例となっています.今年は,修士2年の先輩と,学類4年の白鶺鴒の2人で伊豆大島行きの旅行を企画しました.「旅と鉄道の会」と聞くと,鉄道で旅行に行くことを思い浮かべる方も多いかもしれませんが,行き先や移動手段は問いません.今回はあえて,これまでほとんど行なってこなかった船の旅.学類1年生から修士2年生までの6人で伊豆大島を訪れた際の旅行記を書き綴りました.
2.大型客船で伊豆大島へ
2024年3月16日の夜,旅の始まりは,東京の竹芝客船ターミナルです.ゆりかもめの竹芝駅のほか,JR浜松町駅からもペデストリアンデッキでアクセスできます.ここから,東海汽船が運行する大型客船「さるびあ丸」に乗船し,船内泊で伊豆大島を目指します.私たちが予約したのは大部屋の2等和室で,色で区切られたカーペットの上で寝るという,いかにも客船らしいスタイルです.枕がついているほか,有料で毛布も借りられるので,快適に過ごすことができます.他にも,椅子席や個室など様々な部屋のバリエーションがあり,シャワー室や食堂,エレベーターもついています.まるでホテルのように様々な設備があるのも,大型客船の醍醐味です.
22:00に出航し,伊豆大島に向けて8時間の船旅が始まりました.早速デッキに上がって外の景色を眺めます.はじめは,東京の臨海部を横目に東京湾を進みます.まず目に飛び込んで来るのは東京の夜景です.夜10時を回り,高層オフィスビルの明かりは少なくなってきた一方,赤々とライトアップされた東京タワーがひと際輝きを放っていました.ライトアップされたレインボーブリッジをくぐると,大井ふ頭が見えてきます.コンテナを積み下ろしするガントリークレーンの夜景は,船でしか味わえない光景です.夜景観賞がひと段落したところで,翌日に備えて就寝しましたが,途中横浜にも寄港したそうです.
ところで,伊豆大島でフェリーが到着する港は,その日の天候次第で変わるといいます.中心部に近い元町港と,大島公園など島の北東部へのアクセスが良い岡田港があり,今回は岡田港に発着しました.
ところで,伊豆大島でフェリーが到着する港は,その日の天候次第で変わるといいます.中心部に近い元町港と,大島公園など島の北東部へのアクセスが良い岡田港があり,今回は岡田港に発着しました.
3.バスで島内巡り
3.1 まずは朝食
翌朝6時,ほぼ定刻で伊豆大島の岡田港に到着しました.ここからは大島バスの路線バスを使って島内を巡っていきます.下船すると,バスロータリーに島内の各方面へ向かう路線バスが待機しており,フェリーの乗客は待ち時間なく目的地へ移動できます.一行は,朝食をとるために元町港方面へのバスに乗り込みました.向かったのは,元町港から数百mのところにある御神火温泉という日帰り入浴施設.フェリーの到着に合わせて,朝早くから営業していました.食堂も併設されており,私は島海苔の入ったお粥をいただきました.
3.2 波浮港
翌朝6時,ほぼ定刻で伊豆大島の岡田港に到着しました.ここからは大島バスの路線バスを使って島内を巡っていきます.下船すると,バスロータリーに島内の各方面へ向かう路線バスが待機しており,フェリーの乗客は待ち時間なく目的地へ移動できます.一行は,朝食をとるために元町港方面へのバスに乗り込みました.向かったのは,元町港から数百mのところにある御神火温泉という日帰り入浴施設.フェリーの到着に合わせて,朝早くから営業していました.食堂も併設されており,私は島海苔の入ったお粥をいただきました.
3.2 波浮港
ここから,一行は二手に分かれて行動することに.一方は,御神火温泉に入った後に,バームクーヘンとも称される地層切断面へ,もう一方は温泉には入らずより元町港から離れた場所にある波浮港という港町へ散策に行きました.私は後者を選択し,朝食後すぐに元町港へ歩いて向かい,7:20発の波浮港方面行きのバスに乗り込みました.波浮港は,火山爆発によって生まれたマールという火山地形を活かして,1800 年頃に開港しました.周囲が切り立った崖で風を避けられるため「風待ち港」とも呼ばれ,昭和の半ばまで多くの漁船の中継地となっていたそうです.歌人や作家もこの地を訪れ,野口雨情の「波浮の港」をはじめ,大島をテーマにした作品を残しています.現在は,風情ある漁港の集落が残っています.
そんな波浮港をまずは崖の上から見下ろしてみましょう.崖に囲まれたくぼ地が湾のようになり,海岸と崖の間のわずかなスペース,そして崖の上にも集落があります.他の場所で見たこともないような不思議な地形でした.ここから港のほうへ下って行ったのですが,途中で「クダッチ」という名前が書かれた交差点を発見.先ほど乗ってきたバスには「下地」というバス停,ガソリンスタンドには「下ツ地SS」と書いてありました.初見ではとても読めませんね…難読ゆえカタカナ表記になったのでしょう.波浮港には小さな神社があり,その横から海辺に近づくことができます.地元の若者たちが磯遊びをしていたほかは人影がまばらで,ただ波が岸に打ち付ける音だけが聞こえてきました.
3.3 泉津の切通し
そんな波浮港をまずは崖の上から見下ろしてみましょう.崖に囲まれたくぼ地が湾のようになり,海岸と崖の間のわずかなスペース,そして崖の上にも集落があります.他の場所で見たこともないような不思議な地形でした.ここから港のほうへ下って行ったのですが,途中で「クダッチ」という名前が書かれた交差点を発見.先ほど乗ってきたバスには「下地」というバス停,ガソリンスタンドには「下ツ地SS」と書いてありました.初見ではとても読めませんね…難読ゆえカタカナ表記になったのでしょう.波浮港には小さな神社があり,その横から海辺に近づくことができます.地元の若者たちが磯遊びをしていたほかは人影がまばらで,ただ波が岸に打ち付ける音だけが聞こえてきました.
3.3 泉津の切通し
さて,波浮港を一通り見終えたところで,波浮港8:39発のバスで元町港へ戻ります.途中の地層切断面でもう一方のグループと合流し,ここからは全員で行動しました.元町港でバスを乗り継ぎ,9:44に泉津にて途中下車.ここからしばらく歩くと,泉津の切通しというパワースポットがあります.道路脇に,ほぼ左右対称となった2本の照葉樹の巨木が植わっており,その根に覆われた岩山の間に細い農道が通っています.周辺は苔で覆われ緑色の薄暗い空間が広がっており,奥へ分け入っていくと異世界へとつながってしまいそうな,独特の雰囲気を醸し出していました.
3.4 大島公園
泉津の切通し最寄りの椿トンネルバス停から再びバスに乗車し,11:34に大島公園に到着しました.ここには,伊豆大島名物の椿を展示している椿園や,動物園があり,中でも広さ 7ha の椿園には,園芸品種約 450 種 3,700 本が植えられているほか,ヤブツバキ約 5,000 本が自生しており,国際優秀つばき園にも認定されています.椿はちょうど見頃を迎え,薄紅色,まだら模様,八重咲など,様々な色や形の椿が咲いていたほか,椿に特化した資料館もあり,大島での椿栽培の歴史も学ぶことができました.椿に混ざってハクモクレンやオオシマザクラも見頃となっているものもあり,春の訪れを存分に感じることができました.動物園にはバードケージやサル山があり,動物たちの生き生きとした姿を間近で観察することができました.園内の歩道からは海を望むことができる,絶好のロケーションにも恵まれています.
3.5 三原山
3.4 大島公園
泉津の切通し最寄りの椿トンネルバス停から再びバスに乗車し,11:34に大島公園に到着しました.ここには,伊豆大島名物の椿を展示している椿園や,動物園があり,中でも広さ 7ha の椿園には,園芸品種約 450 種 3,700 本が植えられているほか,ヤブツバキ約 5,000 本が自生しており,国際優秀つばき園にも認定されています.椿はちょうど見頃を迎え,薄紅色,まだら模様,八重咲など,様々な色や形の椿が咲いていたほか,椿に特化した資料館もあり,大島での椿栽培の歴史も学ぶことができました.椿に混ざってハクモクレンやオオシマザクラも見頃となっているものもあり,春の訪れを存分に感じることができました.動物園にはバードケージやサル山があり,動物たちの生き生きとした姿を間近で観察することができました.園内の歩道からは海を望むことができる,絶好のロケーションにも恵まれています.
3.5 三原山
最後に訪れたのは,伊豆大島の中央にそびえる活火山,三原山です.標高 758m の活火山で,現在の山頂は江戸時代の安永噴火でできたそうです.約 35 年に一度は比較的大きな噴火が起きており.噴火による火柱や火映は「御神火(ごじんか)様」として信仰の対象となっているそうです.そんな三原山には,外輪山の展望台までバスでアクセスできます.
大島公園発12:40のバスで出発し,三原山を登っていきます.途中,火口を望むことができる展望台の前で減速したり,車内の自動放送で三原山の案内が流れたりと,観光客にとってうれしいサービスが盛りだくさんでした.終点の三原山頂口には13:00に到着し,ここで昼食休憩としました.入ったのは,元町港方面を一望できるレストラン「歌乃茶屋」さん.店内は土産物コーナーの奥に長机形式の食堂があるレイアウトで,昭和のよき雰囲気が漂っていました.注文したのは島海苔そばで,他にも明日葉の天ぷらなど,地元食材を使ったメニューが豊富です.席からは,元町港方面を眼下に眺めることができました.
三原山の見学を終え,いよいよ最後のバスで岡田港へと戻りました.
大島公園発12:40のバスで出発し,三原山を登っていきます.途中,火口を望むことができる展望台の前で減速したり,車内の自動放送で三原山の案内が流れたりと,観光客にとってうれしいサービスが盛りだくさんでした.終点の三原山頂口には13:00に到着し,ここで昼食休憩としました.入ったのは,元町港方面を一望できるレストラン「歌乃茶屋」さん.店内は土産物コーナーの奥に長机形式の食堂があるレイアウトで,昭和のよき雰囲気が漂っていました.注文したのは島海苔そばで,他にも明日葉の天ぷらなど,地元食材を使ったメニューが豊富です.席からは,元町港方面を眼下に眺めることができました.
三原山の見学を終え,いよいよ最後のバスで岡田港へと戻りました.
4.ジェット船で帰途へ
帰りは,同じく東海汽船ですが,往きと異なり高速ジェット船「セブンアイランド」を利用しました.乗船代を少しでも安く抑えるため,竹芝まで行かずに途中の神奈川県の久里浜まで乗船し,そこから電車を使うことに.それでも,品川までの所要時間は3時間程度と,往きの半分以下で済みます.なぜこんなにジェット船は速いのでしょうか?
ジェット船の正式名称はジェットフォイルで,アメリカの航空機メーカーが開発したものです.その名の通り,ジェットエンジンで海水を吹き出し,海水から揚力を得て船体を水面上に浮かせて走ります(これを翼走というそう).これによって,時速80km/hという高速で,かつ船酔いをしにくい滑らかな航行ができる,というわけです.
ジェット船の正式名称はジェットフォイルで,アメリカの航空機メーカーが開発したものです.その名の通り,ジェットエンジンで海水を吹き出し,海水から揚力を得て船体を水面上に浮かせて走ります(これを翼走というそう).これによって,時速80km/hという高速で,かつ船酔いをしにくい滑らかな航行ができる,というわけです.
15:30,伊豆大島に別れを告げて,岡田港を後にしました.出航して間もなく,飛行機の離陸時のようなエンジン音を轟かせながら加速し始め,しばらくすると船体が水面から浮き上がりました.翼走中は,波を受けるとき以外は安定していましたが,高速で航行するため,シートベルトの着用が求められます.まるで飛行機です.しばらく外を眺めていると,右手に房総半島,左手に三浦半島が見えてきました.久里浜には16:30着.往きに一晩を越したのがうそのような,あっという間の船旅でした.しかし,久里浜港から京急久里浜駅までちょうど良いバスがなく,片道2kmを歩かざるをえませんでした.ただ,これまで久里浜を訪れたことがなく,初めて訪れたまちを歩けるという楽しみが疲れを上回りました.途中,自動車教習所が併設されたショッピングセンターがあり,意外な組合せに驚きました.アーケードに差し掛かると,間もなく京急久里浜駅に到着しました.ここからは,京急線の快特に揺られそのまま品川へ向かい,各自の自宅へ帰着しました.
5.おわりに
今回は,「旅と鉄道の会」としては珍しい船とバスの旅で,伊豆大島を巡ってきました.火山が生み出した地形やそれに適応して暮らす人々の営みなど,東京出身者として,ここが東京都内であることを忘れてしまうような風景に出会い,新たな東京の側面を発見することができたと思います.
また,今回の旅行をもって修士2年生の先輩お一人がたびてつを卒業されました.これまで新歓や学園祭などで多くのアドバイスをいただき,コロナ禍以降のサークル活動の立て直しに経験者として助け舟を出してくださいました.ここに感謝の意を表するとともに,新たな場所でのご活躍をお祈り申し上げます.
また,今回の旅行をもって修士2年生の先輩お一人がたびてつを卒業されました.これまで新歓や学園祭などで多くのアドバイスをいただき,コロナ禍以降のサークル活動の立て直しに経験者として助け舟を出してくださいました.ここに感謝の意を表するとともに,新たな場所でのご活躍をお祈り申し上げます.