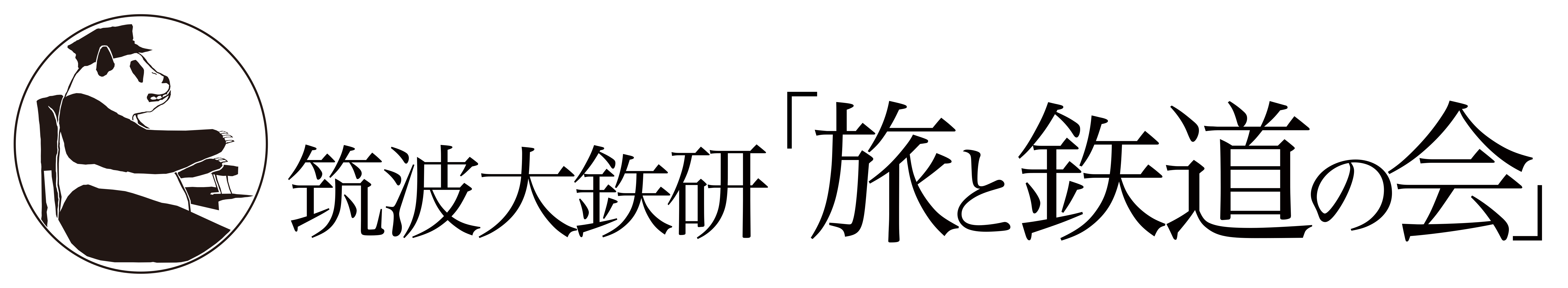日帰り静岡旅行記
旅人 動輪径27インチ
日本でもっとも有名なフリーきっぷ、青春18きっぷ。JRの普通列車自由席が乗り放題となるもので、春夏冬と年間3回の期間ごとに発売され、5回分セットで12,050円である。
私は今年の夏、てっけんサミットのための東北行(当キドリ別記事参照)を主目的に青春18きっぷを購入し、使用した。1回目が茨城県北(写真部の遠足)を経由しての帰省、2回目が銚子、3・4回目がサミットの往復、そして5回目が今回紹介する静岡旅行である。
9月9日月曜日、私は7時頃実家を出発した。サミットから帰宅した翌日であるが、18きっぷの有効期限が翌10日に迫るなか、天気の関係でこの日を選ぶことになったのだ。
遅れ気味の東海道線を平塚、小田原と乗り換え、熱海に着く。途中の湯河原には運用を離脱したE217系が留置されていた。熱海から乗るのは10:10発の伊東線、伊豆急行線直通伊豆急下田行の209系改め伊豆急3000系である。海岸に張り出した山々をトンネルで抜け、10:36に伊東に到着、ここで降車した。すぐには改札を出ず、上りの普通列車を待つ。幸運なことに、その編成の熱海寄り半分は無塗装のTA-7編成であった。
日本でもっとも有名なフリーきっぷ、青春18きっぷ。JRの普通列車自由席が乗り放題となるもので、春夏冬と年間3回の期間ごとに発売され、5回分セットで12,050円である。
私は今年の夏、てっけんサミットのための東北行(当キドリ別記事参照)を主目的に青春18きっぷを購入し、使用した。1回目が茨城県北(写真部の遠足)を経由しての帰省、2回目が銚子、3・4回目がサミットの往復、そして5回目が今回紹介する静岡旅行である。
9月9日月曜日、私は7時頃実家を出発した。サミットから帰宅した翌日であるが、18きっぷの有効期限が翌10日に迫るなか、天気の関係でこの日を選ぶことになったのだ。
遅れ気味の東海道線を平塚、小田原と乗り換え、熱海に着く。途中の湯河原には運用を離脱したE217系が留置されていた。熱海から乗るのは10:10発の伊東線、伊豆急行線直通伊豆急下田行の209系改め伊豆急3000系である。海岸に張り出した山々をトンネルで抜け、10:36に伊東に到着、ここで降車した。すぐには改札を出ず、上りの普通列車を待つ。幸運なことに、その編成の熱海寄り半分は無塗装のTA-7編成であった。


シーズンが終わり解体作業が行われている海の家を横目に、海岸に出る。ちょうどよいところに短い突堤があり、先端に進んで海とテトラポッドを撮った。私はテトラポッドが好きだ。コンクリートの質感がたまらない。

日陰を求めながら街を歩き、シラス丼を食してから駅に戻る。バスターミナルは昨年の新春旅行で訪れた修善寺駅や伊豆急下田駅と同様、バックで進入したバスが横に並ぶ形態であった。東海バスの十八番なのだろうか。小さい頃読んでいた『うみへいくピン・ポン・バス』(竹下文子・作 鈴木まもる・絵)の一場面がふと頭に浮かぶ。
ホーム上屋とサフィール踊り子・黒船電車を眺めてから、12:53に伊東を発つ。今度は伊豆急カラーの8000系。熱海に着いてから両先頭車をよくよく見ると、元からの先頭車と改造車との間で前頭部側面のビードや前面の飾り帯、急行灯の有無に違いがあることが見てとれた。
ホーム上屋とサフィール踊り子・黒船電車を眺めてから、12:53に伊東を発つ。今度は伊豆急カラーの8000系。熱海に着いてから両先頭車をよくよく見ると、元からの先頭車と改造車との間で前頭部側面のビードや前面の飾り帯、急行灯の有無に違いがあることが見てとれた。

伊豆を後にし、次は西に向かう。14:29に吉原駅に降り立った。ホームからは岳南電車が見えるとともに、北東側に隣接する製紙工場、特にその紅白の煙突がよく目立っていた。南側にはまた、側線の向こうにJR東海カラーのウニモグがぽつんと止まっている。


駅を出て外を歩く。岳南電車の駅舎はJRからは離れたところにある小さなもので、街は住宅と工場、駐車場からなっていた。見えはしないが海が近く、津波避難タワーもある。製紙工場の北側に回った帰りにふと見ると、いったいいつごろのものだろうか、道の分岐点にあるコンクリート壁に「国鉄吉原駅← →田子の浦港」の文字と黄色の縞模様が塗ってあった。
再び列車に乗り、一駅移動する。駅間からもいくつかの製紙工場が見え、着いた富士駅にはコンテナが並ぶ貨物駅が併設されていた。改札内に戻り、373系の特急ふじかわを眺める。両開き扉であるうえ、車体はビード入りのステンレスがむき出しになっていて、特急より少し気軽な印象である。急行の後継としてある種ふさわしい。
16:20、身延線で富士駅を発つ。東海道線から離れると富士山を真正面にしてしばらく進み、富士宮を擁する別の谷筋で標高を稼いでから富士川沿いに出る。富士川の谷は狭く、身延線は斜面の下の方に張り付くようにして走っている。反対側には勾配のついた高速道路が高い橋脚を伸ばして通っているさまも見てとれた。山に囲まれている割にはしかし川幅は広い。上流に大きな盆地を抱えているがゆえのことであろう。学生を中心とした乗客は富士宮を過ぎるとだんだんと減ってゆき、退勤ラッシュの甲府盆地に入ると再び立ち客が出るまでになった。
19:16、甲府着。211系で大月まで進み、そこからE233系に乗り換え、旅を終えた。
再び列車に乗り、一駅移動する。駅間からもいくつかの製紙工場が見え、着いた富士駅にはコンテナが並ぶ貨物駅が併設されていた。改札内に戻り、373系の特急ふじかわを眺める。両開き扉であるうえ、車体はビード入りのステンレスがむき出しになっていて、特急より少し気軽な印象である。急行の後継としてある種ふさわしい。
16:20、身延線で富士駅を発つ。東海道線から離れると富士山を真正面にしてしばらく進み、富士宮を擁する別の谷筋で標高を稼いでから富士川沿いに出る。富士川の谷は狭く、身延線は斜面の下の方に張り付くようにして走っている。反対側には勾配のついた高速道路が高い橋脚を伸ばして通っているさまも見てとれた。山に囲まれている割にはしかし川幅は広い。上流に大きな盆地を抱えているがゆえのことであろう。学生を中心とした乗客は富士宮を過ぎるとだんだんと減ってゆき、退勤ラッシュの甲府盆地に入ると再び立ち客が出るまでになった。
19:16、甲府着。211系で大月まで進み、そこからE233系に乗り換え、旅を終えた。