
Twitterブログパーツ

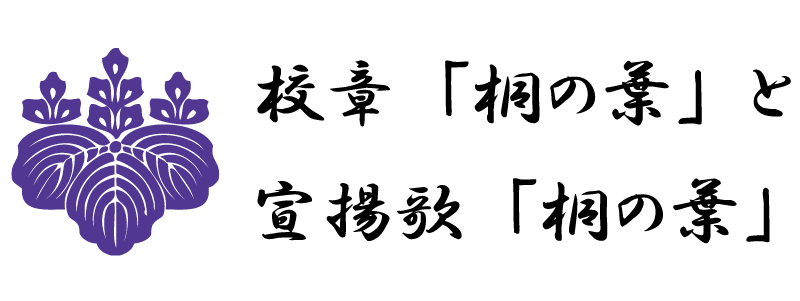
| |||
|
|
筑波大学校章「桐の葉」筑波大学は昭和48年(1973)に創設された新しい大学ですが、その歴史は明治5年(1872)、現在の御茶ノ水(茗渓)に作られた師範学校(教員養成学校)まで遡ることができます。 明治36年(1903)年に、「五三ノ桐葉形」、すなわち「桐の葉」が校章となりました。桐葉形の紋章は日本古来より貴人の紋章であり、現在でも内閣総理大臣の紋章として使われています。 東京高等師範学校の帽子の徽章は当初十六弁の菊花紋様に「高師」の字を配したものでしたが、明治36年(1903)7月に生徒制服が改正された時に、 「全形五三ノ桐葉形ヲ金色トシテ 中央ニ高師ノ二字ヲ磨キトス(全形竪一寸一分横一寸一分五厘)」 と、「桐の葉」を用いることになりました。 この「桐の葉」は昭和24年(1949)の東京教育大学学生バッジに受け継がれ、昭和49年(1974)、筑波大学開学の際に校章として制定されました。そして開学25周年を迎えた平成11年(1999)、複数あったデザインを統一し、現在の形となりました。 筑波大学宣揚歌「桐の葉」明治の終わりから大正時代にかけて、東京高等商業学校(現在の一橋大学)などで、大学昇格を求める声が強まっていました。 桐の葉は木に朽ちんより、秋来なば先駆散らん 日本の教育を担う高等師範が尊重されないのであれば、廃校も辞さず、という勇ましい決意を込めた歌は昔の応援歌の曲譜に載せて瞬く間に学内に広がり、学生の愛唱歌となりました。 大学昇格運動の結果、東京文理科大学が設置され、戦後の昭和24年(1949)に東京教育大学が成立しました。 年を経て 百年過ぎぬ 今ここに 水は渇るとも 新泉は 筑波の麓に いざ立たん 若人われら 東京大塚の地の歴史はここに終わるが、茗渓の歴史の流れは新天地筑波で永遠に続いていってほしい、宣揚歌には当時のそんな願いを込められています。 おことわり:この文章の大部分は弊部の内部書類を元にしたものであり、歴史的経緯が全て正確であることは保証できないことをご了承ください。 |
||