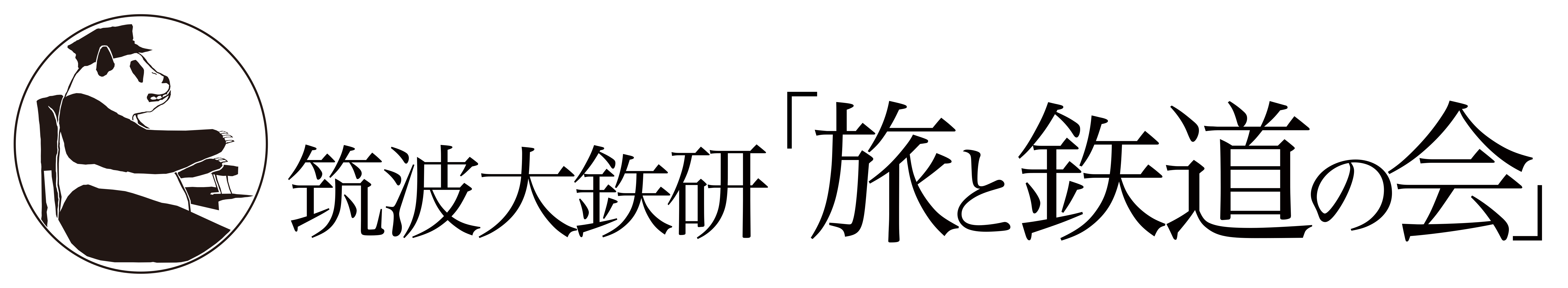常磐新線の模型を1か月で作る
旅人 中扉締切
今年でつくばエクスプレス、TXは開業20年を迎えた。原野、田畑、あるいは空き地ばかりだった沿線にはすっかり建物が立ち並んでミチミチになり、外見上ほぼ二種類しかいなかった車両は増備と改造でバリエーション豊かになった。全線通しの普通電車が極端に少なく、快速がビュンビュン走っていたダイヤも、次第につくば発着の普通電車の本数が増え、沿線に多くの人の暮らしが根付いたことを実感する。
そんなある日、たびてつに模型展示のオファーが飛び込んできた。TX開業20周年を記念して、駅前のホテル日航つくばのロビーで8月9~11日にNゲージを走らせるというものだ。TXの記念なのだから、当然TXの模型が望ましいだろう。しかし困った。TXの模型がない。後輩が持っているのと合わせて2本しかない。私自身が常磐線ばかり使っていてTXに馴染みがなく、TXの模型も比較的高価で整備が難しいため敬遠しがちだったのだ。
TX といえば複線の高架線路だ。しかも N ゲージは常時走らせっぱなしにするといけないので、それぞれの線路に対して待機する予備の車両が必要だ。したがって最低限 4 本の車両が必要になる。2本足りない。常磐線の模型ならそこそこ持っているが、6両のTXに対して常磐線は5両・10両・15両だし、TXにないグリーン車が目立って釣り合いがとれない。子供受けする特急ひたちも、派手なデザインでなおさら釣り合わない。
不足する2本の車両のうちの1本としては、TX-1000系の模型を購入することにした。TXの車両は外見上4種類ある。直流電源専用で守谷以南にしか入らないTX-1000系14本、TX-1000 系とほぼ同じ塗装だが交流電源に対応し屋根上・床下の装備が多いTX-2000系初期車16本、側面腰部に赤と白のラインが入ったTX-2000系増備車7本(現存6本)、そして赤と青のラインが目立つ最新鋭のTX-3000系5本だ。後輩が持っている車両はTX-2000系増備車とTX-3000系なので、役回りは地味な車両だがTXの基本を抑えた選択肢だ。
今年でつくばエクスプレス、TXは開業20年を迎えた。原野、田畑、あるいは空き地ばかりだった沿線にはすっかり建物が立ち並んでミチミチになり、外見上ほぼ二種類しかいなかった車両は増備と改造でバリエーション豊かになった。全線通しの普通電車が極端に少なく、快速がビュンビュン走っていたダイヤも、次第につくば発着の普通電車の本数が増え、沿線に多くの人の暮らしが根付いたことを実感する。
そんなある日、たびてつに模型展示のオファーが飛び込んできた。TX開業20周年を記念して、駅前のホテル日航つくばのロビーで8月9~11日にNゲージを走らせるというものだ。TXの記念なのだから、当然TXの模型が望ましいだろう。しかし困った。TXの模型がない。後輩が持っているのと合わせて2本しかない。私自身が常磐線ばかり使っていてTXに馴染みがなく、TXの模型も比較的高価で整備が難しいため敬遠しがちだったのだ。
TX といえば複線の高架線路だ。しかも N ゲージは常時走らせっぱなしにするといけないので、それぞれの線路に対して待機する予備の車両が必要だ。したがって最低限 4 本の車両が必要になる。2本足りない。常磐線の模型ならそこそこ持っているが、6両のTXに対して常磐線は5両・10両・15両だし、TXにないグリーン車が目立って釣り合いがとれない。子供受けする特急ひたちも、派手なデザインでなおさら釣り合わない。
不足する2本の車両のうちの1本としては、TX-1000系の模型を購入することにした。TXの車両は外見上4種類ある。直流電源専用で守谷以南にしか入らないTX-1000系14本、TX-1000 系とほぼ同じ塗装だが交流電源に対応し屋根上・床下の装備が多いTX-2000系初期車16本、側面腰部に赤と白のラインが入ったTX-2000系増備車7本(現存6本)、そして赤と青のラインが目立つ最新鋭のTX-3000系5本だ。後輩が持っている車両はTX-2000系増備車とTX-3000系なので、役回りは地味な車両だがTXの基本を抑えた選択肢だ。
.jpeg) TX-1000 系(左)と筆者製作の常磐新線(右)
TX-1000 系(左)と筆者製作の常磐新線(右)
残る 1 本だが、被らない選択肢という観点では TX-2000 系初期車がベストだ。しかし初期車の模型は入手困難で、秋葉原を探し回っても見つからない。実物は最多グループだが、模型としての発売のチャンスは増備車と奪い合いになり、見た目がTX-1000系と大差ない初期車はなかなか生産されないのだ。探せばあるかもしれないが、1本2万円以上するTXの模型を一気に 2 本購入するのは流石につらい。
このときには、とりあえず過半数は押さえたからいいや、という思いがあった。残り 1 本は同じアルミ車の東京メトロ千代田線を入れようか、それとも同じ 6 両のエクスプレスだから成田エクスプレスにしようかなどと思っていた。
しかし7月11日、TXにTXという名前がつく前、常磐新線の計画を推進していた段階でのイメージイラストの車両の画像が目に入り、無性に作りたくなった。
現行のTX車両とは似ても似つかない、オーストラリア・シドニー近郊のTangara電車や東京モノレール1000形を思い起こさせる黄色の傾斜した前面。両開き3ドアの車体に、ドア部を上下に貫く黄色の帯。車体下部はそのまま床下を覆うカバー。そして大きな車体断面にそのまま組み込まれた 2 階建て車両。その側面に施されたカラフルな装飾。しかもこの車両は16番ゲージの模型が製作されていて、総合基地での過去のイベントで公開された模型の画像も複数鮮明に残っていた。模型は2編成製作されており、2階建て車両を組み込んだ車体断面の大きな4両編成と、屋根が低く冷房装置が外付けの2両編成があった。大断面の先頭車は、パンタグラフが入る部分の屋根がくり抜かれ、E1系・E4系を思い起こさせる。足回りには空気ばねを備えた両抱き式ブレーキのアルストムリンク台車が収まり、私鉄電車としての時代背景を感じさせる。交直流電車としての実現可能性はさておき、シンプルな形状に詰まった、近未来の電車と新線への夢と期待が伺えた。
気がついたらCADを触っていた。中央線グリーン車で作った車体断面を手直しして車体の塊を作り、シェル機能で箱にし、窓とドアを打ち抜いていく。床下がカバーで覆われ、屋根上もエアコンがないので、ディテールに悩む必要がない。カバーの底面をつなげば床板は車端部だけで済むので、製作中の他の車種のものをベースにしつつ、床下カバーの前後の端とつなげた。車体の3Dモデルは2日で完成した。16番ゲージの模型は先頭車と2階建て中間車の4両、イメージパースでも1階建ての中間車を1両加えた5両だが、他のTXの車両と合わせた6両編成での展示のため、1階建ての中間車をもう1両追加し、前後対称な6 両編成とした。16番ゲージと同様に最短2両での実演が可能なよう動力装置は先頭車に組み込み、各車両の台車には特徴に合致した小田急1000形用のFS534を用意した。
データの完成に合わせて、3Dプリントを開始した。使用した3Dプリンタは光造形方式のElegoo Mars 2 Pro・材料はSK本舗の透明の水洗いレジンで、車体は一端の妻面全体にサポート材をつけ、垂直に出力し、出力後にやすりで修正した。水洗いレジンは水に触れると膨張し、乾燥すると収縮するため、その過程のどこかで一点に歪みが集中するとそこから裂けてしまう。3Dデータの段階で車体の厚みを原則1.5 mm以上としたことが功を奏し、大きな手直しを要する失敗はなかった。しかし積層や乾燥に失敗してヒビが入った車体があり、最大3回ほど出力をやり直した。特に動力車はKATO製品を前提にして設計した結果、側面の厚みが不足し洗浄後の乾燥工程で裂けてしまったため、幅の狭いグリーンマックス製動力ユニット用に再設計した。また、大きな窓による車体の若干の歪みは許容した。
車体が厚いことから、窓ガラスもアクリル削り出しとすることを検討した。比較的安価なCNCフライスを購入し、材料のアクリル板も用意してはいたが、扱いに不慣れなことと時間の不足により、見送ることとした。側面ガラスは車体の裏面からPET樹脂の透明プラ板を貼り、前面ガラスはサイズを合わせて車体の表面からはめ込んだ。
車体の塗装・装飾は、屋根のグレー・前面とドアの黄色・車体の銀色・前面の黒をエアブラシによる吹き付け塗装、ライト類を筆塗り、2階建て車両の装飾をステッカーとした。
塗装は下地を兼ねてグレーを車体の全面に塗装したのち、黄色・銀色、そして先頭車の前面のみ黒を、それぞれマスキングしながら塗装したのち、先頭車はライトの色入れを行った。
吹き付けた塗料はMr.カラーで、グレーはニュートラルグレー、黄色はキャラクターイエロー、銀色は銀、黒はウイノーブラックを使用した。ヘッド・テールライトの色入れはタミヤのエナメル塗料で、両方に銀色を塗ったのちテールライトにクリアーレッドを重ねた。
塗装の乾燥を待ちながら、2階建て車両の側面用のステッカーを家庭用のラベルシールで製作した。図案は、側面中央を横切るカラフルなパターンと、2階建て車両同士の連結部分をまたいで半円ずつ描かれた幾何学模様に分けて制作した。
カラフルなパターンは直接GIMP で作成した。正確な色調は不明瞭なものの、2両かつ両側面で配色が異なっていた。模型の側面の写真と照らし合わせつつ、CADデータに寸法を合わせて再現した。連結部分の幾何学模様は拡大・縮小と回転を伴うため、ベクターデータとして一旦Keynoteで製作してPDF化し、GIMPに貼り付けて印刷した。
このときには、とりあえず過半数は押さえたからいいや、という思いがあった。残り 1 本は同じアルミ車の東京メトロ千代田線を入れようか、それとも同じ 6 両のエクスプレスだから成田エクスプレスにしようかなどと思っていた。
しかし7月11日、TXにTXという名前がつく前、常磐新線の計画を推進していた段階でのイメージイラストの車両の画像が目に入り、無性に作りたくなった。
現行のTX車両とは似ても似つかない、オーストラリア・シドニー近郊のTangara電車や東京モノレール1000形を思い起こさせる黄色の傾斜した前面。両開き3ドアの車体に、ドア部を上下に貫く黄色の帯。車体下部はそのまま床下を覆うカバー。そして大きな車体断面にそのまま組み込まれた 2 階建て車両。その側面に施されたカラフルな装飾。しかもこの車両は16番ゲージの模型が製作されていて、総合基地での過去のイベントで公開された模型の画像も複数鮮明に残っていた。模型は2編成製作されており、2階建て車両を組み込んだ車体断面の大きな4両編成と、屋根が低く冷房装置が外付けの2両編成があった。大断面の先頭車は、パンタグラフが入る部分の屋根がくり抜かれ、E1系・E4系を思い起こさせる。足回りには空気ばねを備えた両抱き式ブレーキのアルストムリンク台車が収まり、私鉄電車としての時代背景を感じさせる。交直流電車としての実現可能性はさておき、シンプルな形状に詰まった、近未来の電車と新線への夢と期待が伺えた。
気がついたらCADを触っていた。中央線グリーン車で作った車体断面を手直しして車体の塊を作り、シェル機能で箱にし、窓とドアを打ち抜いていく。床下がカバーで覆われ、屋根上もエアコンがないので、ディテールに悩む必要がない。カバーの底面をつなげば床板は車端部だけで済むので、製作中の他の車種のものをベースにしつつ、床下カバーの前後の端とつなげた。車体の3Dモデルは2日で完成した。16番ゲージの模型は先頭車と2階建て中間車の4両、イメージパースでも1階建ての中間車を1両加えた5両だが、他のTXの車両と合わせた6両編成での展示のため、1階建ての中間車をもう1両追加し、前後対称な6 両編成とした。16番ゲージと同様に最短2両での実演が可能なよう動力装置は先頭車に組み込み、各車両の台車には特徴に合致した小田急1000形用のFS534を用意した。
データの完成に合わせて、3Dプリントを開始した。使用した3Dプリンタは光造形方式のElegoo Mars 2 Pro・材料はSK本舗の透明の水洗いレジンで、車体は一端の妻面全体にサポート材をつけ、垂直に出力し、出力後にやすりで修正した。水洗いレジンは水に触れると膨張し、乾燥すると収縮するため、その過程のどこかで一点に歪みが集中するとそこから裂けてしまう。3Dデータの段階で車体の厚みを原則1.5 mm以上としたことが功を奏し、大きな手直しを要する失敗はなかった。しかし積層や乾燥に失敗してヒビが入った車体があり、最大3回ほど出力をやり直した。特に動力車はKATO製品を前提にして設計した結果、側面の厚みが不足し洗浄後の乾燥工程で裂けてしまったため、幅の狭いグリーンマックス製動力ユニット用に再設計した。また、大きな窓による車体の若干の歪みは許容した。
車体が厚いことから、窓ガラスもアクリル削り出しとすることを検討した。比較的安価なCNCフライスを購入し、材料のアクリル板も用意してはいたが、扱いに不慣れなことと時間の不足により、見送ることとした。側面ガラスは車体の裏面からPET樹脂の透明プラ板を貼り、前面ガラスはサイズを合わせて車体の表面からはめ込んだ。
車体の塗装・装飾は、屋根のグレー・前面とドアの黄色・車体の銀色・前面の黒をエアブラシによる吹き付け塗装、ライト類を筆塗り、2階建て車両の装飾をステッカーとした。
塗装は下地を兼ねてグレーを車体の全面に塗装したのち、黄色・銀色、そして先頭車の前面のみ黒を、それぞれマスキングしながら塗装したのち、先頭車はライトの色入れを行った。
吹き付けた塗料はMr.カラーで、グレーはニュートラルグレー、黄色はキャラクターイエロー、銀色は銀、黒はウイノーブラックを使用した。ヘッド・テールライトの色入れはタミヤのエナメル塗料で、両方に銀色を塗ったのちテールライトにクリアーレッドを重ねた。
塗装の乾燥を待ちながら、2階建て車両の側面用のステッカーを家庭用のラベルシールで製作した。図案は、側面中央を横切るカラフルなパターンと、2階建て車両同士の連結部分をまたいで半円ずつ描かれた幾何学模様に分けて制作した。
カラフルなパターンは直接GIMP で作成した。正確な色調は不明瞭なものの、2両かつ両側面で配色が異なっていた。模型の側面の写真と照らし合わせつつ、CADデータに寸法を合わせて再現した。連結部分の幾何学模様は拡大・縮小と回転を伴うため、ベクターデータとして一旦Keynoteで製作してPDF化し、GIMPに貼り付けて印刷した。
.jpeg) 組み立ての完了した常磐新線イメージ車両
組み立ての完了した常磐新線イメージ車両(5 両目の台車は仮のもの)
装飾の終わった車両からガラスの取り付け・組み立てに入った。パンタグラフは本来交流用を使うべきだが、屋根が窪んでおり碍子が見えないため、入手が容易でストックもあったKATOのPS33Cを使用した。車端部の幌と連結器も、それぞれKATOのE231系などで見る汎用品と、ボディマウントのKATOカプラー密連型 #2 を使用した。ウエイトはホームセンターで購入したステンレス製のステーを車体中央部の底面に取り付けた。台車は前述の通りのFS534で、グリーンマックス製のエコノミーキット用である。ただし1両分が不足したため、不足分はKATOのE231系のもので一旦代用して試運転し、直前に交換した。
.jpeg) 試運転に臨む常磐新線イメージ車両
試運転に臨む常磐新線イメージ車両
.jpeg) 展示で並ぶ常磐新線イメージ車両と歴代TX車両のNゲージ模型
展示で並ぶ常磐新線イメージ車両と歴代TX車両のNゲージ模型(手前から常磐新線・TX-1000系・TX-2000系増備車・TX-3000系)
8 月5日、組み立てが完了し、6両編成を組成した。翌6日には試運転を行い、動力車が先頭・後尾のいずれでもレンタルレイアウトを周回できる性能を確認した。不足していた台車も8日には購入・交換でき、完成した姿で9日の模型展示を迎えられた。
迎えたホテル日航つくばのロビーでの模型展示では、快調な走りで無事3日間走りきり、TX公式のSNSでの紹介という栄誉にも与れた。
開始から完成まで1か月弱。奥まった窓・空っぽの車内・点灯しないライト類など、現代水準のNゲージと並べると改善点も多い車両ではあるが、常磐新線の名でTXが背負ってきた夢を現代に再現することで、子どもたちの歩む未来の公共交通への希望を提示し、またこの姿になじみのある人には昔を懐かしむ助けになれたら幸いである。
最後に、つくばエクスプレス線の開業20周年を迎え、素晴らしい企画と貴重な場を提供してくださった首都圏新都市鉄道とホテル日航つくばの皆さまに、この場を借りて感謝の意を表し、結びとしたい。
迎えたホテル日航つくばのロビーでの模型展示では、快調な走りで無事3日間走りきり、TX公式のSNSでの紹介という栄誉にも与れた。
開始から完成まで1か月弱。奥まった窓・空っぽの車内・点灯しないライト類など、現代水準のNゲージと並べると改善点も多い車両ではあるが、常磐新線の名でTXが背負ってきた夢を現代に再現することで、子どもたちの歩む未来の公共交通への希望を提示し、またこの姿になじみのある人には昔を懐かしむ助けになれたら幸いである。
最後に、つくばエクスプレス線の開業20周年を迎え、素晴らしい企画と貴重な場を提供してくださった首都圏新都市鉄道とホテル日航つくばの皆さまに、この場を借りて感謝の意を表し、結びとしたい。