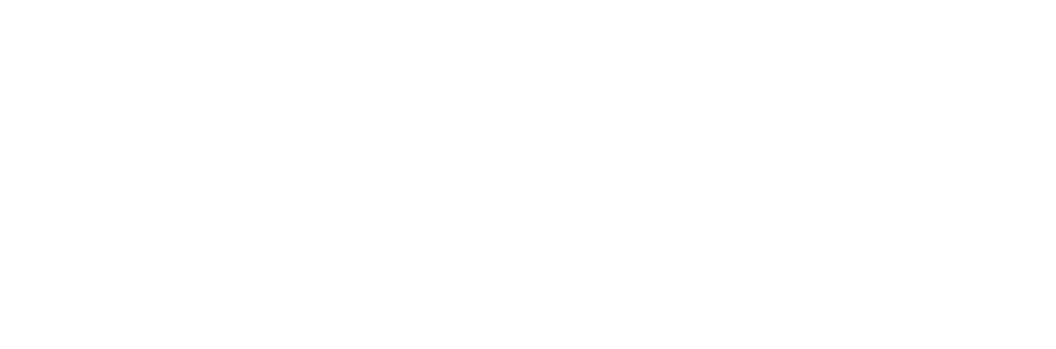正指揮者×副指揮者 スペシャル対談!〜第48回定期演奏会ver.〜
こんにちは!第48回定期演奏会が近づいてきました! スペシャル企画として、正指揮者×副指揮者 スペシャル対談〜第48回定期演奏会ver.をお届けします! 知られざる事実がどんどん明かされていくのでお楽しみに!

宮田裕介
#正指揮者#教育#凝り性
#左側#よく物をなくす
安尾優輝
#副指揮者#工シス#水色帽子#右側#愛ある多忙男
(聞き手:48期ソプラノ難波)
録音されるということで緊張気味の2人…まずはこの質問からいってみます!
それぞれの曲集との出会い
―正指揮曲を選んだきっかけは?
宮田:まず、『たましいのスケジュール』がどのように選ばれたかっていうと、48期の方々全体から曲を募集して、その中で、『たましいのスケジュール』が今のつくこんの雰囲気とか、声に一番合っているという話になって。で、アップテンポな楽しい曲の方が、私が指揮をしたときに一番しっくりくるんじゃないかっていうこともあって。この2点がやっぱり、決め手になりましたね。
で、実際練習が始まってみると、去年よりも難しいっていうか(笑)苦戦はしたんですけれども…本当にやりがいのある曲だなって思ってます。
―いいねいいね。副指揮曲はどうやって選ばれたの?
安尾:えっと、まず去年の夏合宿のときに僕が副指揮者になるって決まって、そこで初めてやりたい混声合唱曲って何だって考え始めたんですね。元々男声合唱ばっかりやってるオタクだったので。そっから混声合唱曲あんま知らねえなっていうことに気づき…。その頃には既に上田真樹先生が大好きだったんですけど、改めて上田先生の混声曲を聴き直したら、とても魅力的な曲が多いということに気づきました。
そこから夏合宿の時点で割と『夢の意味』やりたいなという気持ちがもう既に固まって。そこから同期への裏工作を始め少しずつ洗脳して『夢の意味』を好きにさせていきました
―どんなことしたの?(笑)
安尾:何か、ちょっとずつ洗脳して、ここがいいぞここがいいぞみたいなことを刷り込むっていうようなことをたくさんしました。
―そうなんだ。それ知らんかったな(笑)
宮田:そういうのは多分全部終わってから言った方がいいかもしれないね。とか言って(笑)
安尾:そうですね。まだばれるべきじゃない(笑)
元々僕が混声合唱団に入ったきっかけが上田真樹先生で…47定の正指揮曲の『鎮魂の賦』につられて、のこのこと混声合唱団に入ったんですけど、まさか入団のきっかけとなった上田先生の曲を自分が振ることになるとは思っていませんでした。
―確かに。すごいご縁だね
宮田:そう、彼は何かしら持ってると俺は思ってます(笑)
安尾:もうそろそろ運を使い果たすんじゃないかなって思って生きてるんですけど(笑)
―じゃあ、それぞれの曲集の推しポイントを教えてください。
宮田:今一番好きな曲から先に話して、そっから語るって感じにしようかな。私がこの4曲の中で一番好きなのは、当然2曲目の「たましいのスケジュール」なんですよ。
―へえ。その心は?
宮田:その心は…!?「たましいのスケジュール」が好きな理由は、まず1曲目の「空」が好きなところから話さなくちゃいけなくて、実は(笑)
―…これは長くなりそうだ(笑)
宮田:空の歌詞が、やっぱり私としては一番衝撃。まずいきなり「うそつかないで」って。これ、年齢は明確に示されてませんけど、こんなことを子どもに言われたらどうしようって思うと同時に、自分もこういう、何か、「どうして生きてるんだろう」とか考えた時期もあったなっていうことを、まず最初に思いました。
でも、私たちはなんで生きてるんだろうっていう、どこにも答えがない問題。しかも結構深刻じゃないですかこの問いって。で、この気持ちが自分の中で思い悩んでく中で、やっぱり何とも言えない苦しさがありますよね。曲の前半のその苦しみとは対照的な空が出てきて…そこの何だろう、孤独というか、悲しみというか、無力感…。それがすごい共感できるっていうか、共感できるからこそ、歌い手も聞き手もちょっと何かつらい気持ちになってしまうんじゃないかなって思うぐらい、引き込まれる曲ではあるなと思っています。
で、最後の「おんなじ空を見てるだれかが ひとりでいいからいてほしい その子といつか会えるなら いっしょに話をしてみたい 今日の空の青さのことを」っていうところ。すごい切実な願いだし、ちょっと含みを持たせた終わり方をしてるなっていうのがある。だからこそ、何か、はーってこう胸を打たれるような感じで、こちらも考えてしまう。聞いてる側もつらい気持ちになっちゃうなっていうのがこの曲かな。なんか、そんな気持ちになりませんか?
安尾:いや、なんか最初すごいなって。重いなって。最初に練習したときに。
宮田:そう!何か、歌詞は子ども向けの詩集 (※1)から持ってきているものだと私は思ってるけど、それにしてはテーマが重すぎるっていうか。で、私はここでちょっとつらい気持ちになってしまうんですけど、そこにこの2曲目が来るわけですよね。
「たましいのスケジュール」。まずゆりかごの海のように、本当に心地の良い揺らぎの中に曲が始まる。生まれ落ちる前のたましいは、ぷかぷかと海のそこを泳いでいて…。で、生きている今は人生の意味とかそういうのがわからないって。「何で生きなくちゃいけないんだろう」っていう葛藤を持ってるけど、生まれる前は「こんな人生を送ろうかな」みたいのも考えてたんだっていうのもわかるし。
この曲の中で、なぜ生きるのかっていうのに対して答えを一つ示していて、「あいすること ただそれだけのために」生きているっていう…。なんだろうね、ここを歌うとき、なんとも胸が熱くなるんだよね。
―え、わかる…。歌いこんじゃう。
宮田:なんで生きてるんだろうって考えたときに、「愛するために生きてるんだよ」っていうのは…これだけで何か救われる人がいるんじゃないかなと思いませんか。特にこの1曲目で傷ついた心に、2曲目でそんな、うん、心地よい中でそんなこと言われたら、なんか救われるなぁって…。それが本当に2曲目の推しポイントですね。だから2曲目が好きです。
―「子もりうたの前に」はどういう曲?
宮田:「子もりうたの前に」は、私としてはなんか、挿話的な曲。この詩の主人公が幼いながらに鋭い視点を持っていたことが窺われる一エピソードとしてあるのかなと思います。
特にこの母親の「科学で説明できないものなんてない」っていう決まり文句に対して、「いや、そんなはずはない。」って思っている。いや、私たちも幼い頃は、幽霊の存在とかを信じていたんだろうけど、いつの間にかその感覚を忘れちゃうんだろうな。
決まり文句で脳みそが乾く……何かメッセージ性強いですよねこの曲。何か世間一般に何か認知されてるそういう言説みたいなさ、決まり文句を何か、特に考えずに信じたりしていると、そういうのなんか思考力とか、想像力が枯渇しちゃうよみたいな意味なのかなと思って。「貼り付けたプラスチックみたい」っていうのが、母親の表情がやっぱりすごい非常に人工的で、本物らしさを欠いている。子どもの目にはそういう風に映ったんでしょうね。んー。ちょっとここはね、我々がどう表現するかは、本番をお楽しみくださいって感じかもしれない。(笑)
―むずいよね~
宮田:ここの解釈というか表現方法が何か無限大すぎて(笑)
安尾:何を考えて書いたのが気になりますよね、横山先生が。
―宮田くん的にはどういう解釈?
宮田:歌の方ですか。
―そうそう、「貼り付けたプラスチック」
宮田:「貼り付けたプラスチックみたい」という箇所は、言葉一つ一つを貼り付けるように、少しでこぼこにというか、無機的な感じで表現したい。そこに最後のソロがくることによって、曲の世界が想起されるようなイメージ。
まだ練習してないのもあるけど、いろんな人に歌ってもらうなりして、ついでに、どんなことを考えながら歌ったのかを聞いてみたいと思っている。こういうソロって、みんなが思っている登場人物像がすごいはっきり出てきて面白いなって。
―確かにね。
宮田:みんなにソロを歌ってもらうと、その人なりの登場人物像が鮮明に出てくるんですよ。だからこう歌ってほしいというよりは、みんなのソロを聴きながら人物像に一番合うなと思ったものを選んでいきたいと思っています。
―めっちゃいいと思う
宮田:で、「影絵」ですね。これが非常に難解。特に歌詞が非常に難解。曲調に関しては本当にアップテンポで、対話をするように軽快な曲なんですけどね。
なかなか解釈が難しいんですけど、歌詞を解釈する上で重要なテーマとなってくるのは“光と影のこと”だと思うんです。
これは、歌詞の第3連からの解釈なんですけど、光しか存在しない世界として天国が描かれていて、この曲の主人公は「天国なんかには住んだりしない」と宣言しているんですよ。ここではっきりと意思を表明しているところが、前3曲との変化だなって思ってます。
話を戻しまして・・・
「天国なんかに住んだりしない」ということは、「光も影も存在している今の世界で生きていきたい」ということの裏返しだと思うんですよね。
ここから、「光と影のこと」についてより迫っていきたいと思います。「光と影」って、もちろん文字通り対照的な言葉として捉えることもできますけど、比喩的な意味でも使うことがありますよね。
曲の冒頭から、各パートが対話をするように繰り返されるフレーズ(手放しながら/にらみつける〜の部分)って、そういった世界に溢れている二面性みたいなことを表しているのかなと考えています。世界にはそういった相反すること・二面性を持つもので溢れているわけですよ。嬉しいことがあれば悲しいこともあるし、戸惑いながらも覚悟しなければならないこともある。
―確かに……
宮田:「逆光のなか/今 彼のシルエットはいのちそのもの」という歌詞にも注目したいです。
安尾:曲の中でも、すごく印象的に表現されていますよね。
宮田: 逆光のなかにいるって、なんだかとてつもない困難に果敢に立ち向かっている感じがしませんか。嬉しいこと幸せなことといった光のことだけでなく、苦しみ、悩みといった影のことも、それら全てを一身に受け止めながらも生きている姿が、鮮明に浮かび上がって見えるような気がします。まさに「いのちそのもの」なんですよ。
主人公は死んでも天国に住んだりしない。つまり現世の方で、この二面性というか、対照的な要素を含んでいる世界で生きていくっていうところ。何か強い意志が感じられるなと。ある意味「影絵」は、前の3曲に対する一つの答えを出しているのかなっていう解釈するのがいいのかなと思っていて…そんな気しませんか?
安尾:いや、わかります
宮田:前の3曲がなぜなぜって来たから4曲目で一つ答えを示すんじゃないかなと思うんですよ。だけど、その示し方がやっぱり結構ちょっと哲学的な感じで示されているので、未だに解釈ができてないっていうのが本音ではあるんですけれども…
宮田:ま、でもとにかく4番目の曲は、何かしらの答えを出してるのかなとは思っています。で、一つはやっぱり「なぜ生きなくちゃいけないのか」っていう、ずっと悩んできたけども、最終的にはこういう何だろう…。例えば孤独とか絶望とか影のことも、要素として含んでいるこの世界でやっぱり生きていきたいっていう、一つの自分の強い意志が表明されて、劇的に曲が終わるっていう感じなのかなと思います。
安尾:曲調が軽快である一方で歌う方も難しいし、テーマも何か哲学的に難しいっていう。ああ、考えれば考えるほど分からなくなってきた。
―大変だね指揮者。
宮田:そう…聴くときはいい曲だなって聴けばいいと思うし、歌詞を深く掘っていこうとすればするほど頭を悩ますかもしれないので。そういうときはもうたましいのスケジュールとかを聞いて、はぁーっていうこのさ、胸が温かくなる気持ちで、リセットしています。最後はいらないかもしんないけど(笑)まあいいや。解釈です!ちょっと定演までに頑張って考えて考え続けます。
―考え続けて、がんばれ。ぜひ伝えてください。
わざと歌いにくく書かれている
―副指揮曲はどのような解釈をしているの?
安尾:『夢の意味』っていうのは歌詞の解釈自体は難しくなくて。っていうのも、曲にすることを前提として詩が書き下ろされて、一回耳で聞いたらわかるように全部ひらがなで(歌詞が)書かれてるんですよね。っていうこともあって、その解釈自体は割と一意に解釈自体は定まって、その背景がちょっと違うかなぐらいのイメージ。
組曲全体として割と情景描写の要素が多いんじゃないかなと感じてるんですよね。特に1曲目から3曲目とか明確な主人公がいて、その主人公が見た景色を描写してるみたいなイメージな気がしていて。
1曲目は「ほのぼのとあかるむ」から始まる、主人公が昔お母さんと一緒にいた頃を思い出してるみたいな、すごくあったかい詩なんですけど、これがもうなんか人生の美しさみたいなものを端的に表していて…2曲目がそれに比べて明るく、軽快なテンポで夏の終わりの風景の美しさを表してる曲なんですよ。1曲目2曲目に関しては本当に問いかけとかがあるわけでもなく、何かただ美しいところを描写する、みたいな。
3曲目から一気に起承転結の「転」の部分を持ってくる感じで。もうなんか、(『夢の意味』は)本当に起承転結がわかりやすく構成されてるなっていう感じの組曲なんですけど、「こんなふうな人生の歩み方をしててよかったのか」みたいな、誰もが一度ぐらいは思ったことがあるだろう疑問を問いかけてきて、聞いてる側も歌ってる側もこれを最初に見たときにはっと気づかされるというか。その瞬間1回その人生の美しさを忘れるぐらいみんな疑念に駆られるわけで、その部分への共感があるからこそ、4曲目5曲目が輝くんだと思うんですよね。
宮田:なるほど。

2023年9月5日夏合宿での、上田真樹先生との記念写真。
安尾:なんか、やっぱりそういう経験って誰にでもあるものなんだろうなっていうことに気づかされるというか。なんて言えばいいんだろうな…。何か、人間誰しも生きてたら、今の自分の人生と違うIfルートみたいなものを考えたことが多分ある人が多いわけで
―あるある、あるよ。
安尾:そこへの気持ちが一気に高ぶってるみたいなところがめちゃくちゃな方法で滅茶苦茶に描写されてると思うんですね。
―めちゃくちゃな方法?(笑)
安尾:気持ちの高ぶりを変拍子で表すところとか。あえてめちゃくちゃなふうに聞こえるように(曲を)書いてる、みたいな。計画的に書いてるのはもちろんなんですけど。
宮田:わざと歌いにくいように書いてるって、なんかちょっと衝撃的な発言だったよね(笑)。※2
安尾:わざと歌いにくくすることで歌い手がどうなるかみたいなところまで計算して書かれている。それにどう立ち向かっていくかっていうのは大きな課題だなってあの発言を聞いて思ったんですけど…歌いにくいところを歌いにくそうに歌うのか、いや余裕ですけどみたいな感じで歌うのか、どっちが正解なんだみたいな。でもやっぱりこの問いかけの部分が本当に僕は好きで。
やっぱり人生において生まれる疑念のうちでは、トップレベルに大きいものというか。それこそ『たましいのスケジュール』は死後、輪廻転生の死んでから生まれるまでの方がメインじゃないですか。なんか逆にこっちの迷いは生きてるうちに「人生こんなんでいいのか。」みたいなところにあると思っていて。その辺に関してはこっちの方が俗なんじゃないかなというか。俗って言い方よくないかもしれないけど、実感に近いというか、やっぱり共感させられる部分としてはあるなと思ってて、
宮田:確かに3曲目に関しては、かなりね、なんていうか生々しいというか自分の思いが何か表出されてる感じはありますよね。
安尾:そこで3曲目の最後で、「こんな人生でもいいんだ」みたいな、(何かこういう解釈はもしかしたら良くないかもしれないけど)1曲目から3曲目の主人公は自分の中で解決すると。で、4・5曲目でこの組曲のテーマでもある「生きていることの意味を誰も本当には知らない」っていうところが出てきている。
宮田:いいっすねえ。
正指揮曲と副指揮曲の対比
安尾:僕はこの組曲の裏テーマみたいなものに、「この常世の世界の美しさ」みたいなものがあるんじゃないかなと思っていて。1曲目と2曲目でこの世界の美しさを描写してたのは実は4・5曲目への伏線であって、調が戻っていくんですよね。
1曲目と5曲目が同じ調で 歌われていて、2曲目と4曲目が同じ調で歌われてるんですけど、ちょっとずつ伏線を回収しながら、4・5曲目での疑問に対しての答えが、実は1・2曲目の「この世の中美しいよね。」って言っていた場面で示されていたんだみたいな。
4・5曲目で最初に「なんで生きていくことに本当に意味があるのか」みたいな問いかけが出てくるんですけど、「世の中が美しいから生きていることに意味はあるじゃないか」みたいな結論にやっぱりたどり着いてると思うんですよね。そういうとんでもない伏線の張り方を林先生がされていて。
宮田:面白いな。私は『たましいのスケジュール』の「影絵」では逆に“影”のことも含んでいるこの世界で生きていきたいっていう解釈をしてるからさ、そこの対比もちょっと面白いね。
―対照的だね。
宮田:気付きがあったな。
安尾:この組曲において、美しいから生きているというより、どちらかというと美しいから生きていたいっていう意志の方がやっぱり強い気がするんですよね。この世がもしも夢であってもこんな美しい世界なんだから少しでも長く生きていきたいみたいな「強い意志」があるわけで。
―その言葉好きだよね(笑)
宮田:私も好き
安尾:自分の意志としてのこの表現をいかに詰めていけるかなみたいなところが、指揮者としてのテーマの一つです、僕からすると。
やっぱり詩としての解釈自体はしやすいんですけど、いろんなところに散りばめられている伏線をいかに聞いてる人に「これさっきも聞いたメロディーだ」「さっきも聞いたフレーズだな」みたいな、こことここが繋がってたんだっていう箇所を気付かせるかっていうところ。
宮田:なんかずるいな。
安尾:あざといんですよすごく。こういうの好きなんでしょみたいな。いや、好きなんですけど。強い意志をいかにうまく表現できるかにかかってるなと思わされます。前半情景描写だと思ってたら4・5曲目で強い意志が入ってくるのを、エモいなと思わされちゃうんですよね。この組曲、最後の最後でしか自分の意志を表出していないところもいいなと思ってて、
宮田:なるほど。
安尾:最初聞いて、なんか歌詞聞いても、普通に美しいところを描写してるだけだろうと思ったら最後にどんどんテンション上げてって…まあテンション上がりすぎてちょっとやばいんですけど歌ってる側としては。ちょっと疲れちゃうんですけど
宮田:ちょっと1ステとは思えないぐらいの
安尾:重さです。…解釈としてはこれぐらいですかね。
(2023年秋 筑波大学構内にて)
※1 組曲『たましいのスケジュール』の歌詞を始めとした詩が『海のような大人になる』(理論社)という詩集にまとめられている
※2 夏合宿にて、『夢の意味』を作曲した上田真樹先生から直接指導を受ける機会があり、上田先生は「表現のためにわざと歌いにくい音程やリズムを用いている」という旨の発言をされていた。